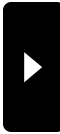2014年 二輪の森 作製
何故か厨子甕(ズシカメ)のアートの魅力に魅かれ
とうとう ミニ厨子甕 作ってしまいました。
材料は紙粘土なんですが、かわいくナイデショウカ??


何故か厨子甕(ズシカメ)のアートの魅力に魅かれ

とうとう ミニ厨子甕 作ってしまいました。

材料は紙粘土なんですが、かわいくナイデショウカ??

2014年2月撮影 沖縄県中頭郡読谷
「厨子甕作ろう体験工房」って工房があるのではと思い
やちむんの里にやってまいりました。
敷地の大きさにびっくり
天気も良く
散歩がてらの工房散策でしたが 厨子甕工房らしいのは見つからず 残念


昔の沖縄にタイムスリップ出来たのでは(^^)
って感じな気分になれました!(^^)
「厨子甕作ろう体験工房」って工房があるのではと思い
やちむんの里にやってまいりました。
敷地の大きさにびっくり

天気も良く

散歩がてらの工房散策でしたが 厨子甕工房らしいのは見つからず 残念



昔の沖縄にタイムスリップ出来たのでは(^^)
って感じな気分になれました!(^^)
2014年2月撮影 沖縄県中頭郡読谷村座喜味708−6
天気も良く ボ-っと城内散策は最高でした!
城壁に気になるカ所発見
1416年-1422年に読谷山の按司護佐丸(ごさまる)が築城したとされている。
城門のアーチに楔石を用いており、アーチ門では古い形態とされる。
恩納村の山田按司の護佐丸 以前に築いた山田城より城壁を運び
座喜味城を築いたとの事です。



写真右側 布積み中央付近

野良積み?

布積み?


透水箇所は劣化が早いかも??
天気も良く ボ-っと城内散策は最高でした!

城壁に気になるカ所発見

1416年-1422年に読谷山の按司護佐丸(ごさまる)が築城したとされている。
城門のアーチに楔石を用いており、アーチ門では古い形態とされる。
恩納村の山田按司の護佐丸 以前に築いた山田城より城壁を運び
座喜味城を築いたとの事です。
写真右側 布積み中央付近

野良積み?
布積み?

透水箇所は劣化が早いかも??
2014年2月撮影 読谷村 座喜味城内にて
厨子甕〜ず(^^)メチャメチャ複数形ですね!
彼らは1700〜1900年代にのタイプでしょうか?芸術ですね〜
かなりアートだと思います
彼らは何故ここに集まっているのか?モアイか?
彼らは現役組?リタイヤ組?OB?おじ〜?(やっぱり)
もしや土建屋で研究会?
とにかくシェイプが素敵なイケメンですね(^^)
※蓋開ける勇気は無かった

続きを読む
厨子甕〜ず(^^)メチャメチャ複数形ですね!
彼らは1700〜1900年代にのタイプでしょうか?芸術ですね〜
かなりアートだと思います

彼らは何故ここに集まっているのか?モアイか?
彼らは現役組?リタイヤ組?OB?おじ〜?(やっぱり)
もしや土建屋で研究会?
とにかくシェイプが素敵なイケメンですね(^^)
※蓋開ける勇気は無かった


続きを読む
2014年2月撮影 南城市佐敷
「シックスセンス友人Yちゃん」の案内のもと
この地にやってまいりました。
なぜYちゃんはココを案内したのでしょう
そういえば チョット前に 交信してた素振りがあった(^^)
いずれキュートなYちゃんブログで紹介したいところです

続きを読む
「シックスセンス友人Yちゃん」の案内のもと
この地にやってまいりました。
なぜYちゃんはココを案内したのでしょう

そういえば チョット前に 交信してた素振りがあった(^^)
いずれキュートなYちゃんブログで紹介したいところです


続きを読む
2014年2月撮影 南城市佐敷
第一尚氏王統 初代 尚思紹 と 二代目 尚巴志 の居城だそうです(^^)
「シックスセンス友人Yちゃん」に即 裏手の拝所に案内され
軍隊のごとく行進し Y軍曹の伝言を一字一句間違えることなく
手をあわせ 願いを投じました
Y軍曹いわく 今日この地に私達が来たことは 何か意味のある
今後必要な事 だそうです(^^)
ありがとう Yちゃん(^^)

続きを読む
第一尚氏王統 初代 尚思紹 と 二代目 尚巴志 の居城だそうです(^^)
「シックスセンス友人Yちゃん」に即 裏手の拝所に案内され
軍隊のごとく行進し Y軍曹の伝言を一字一句間違えることなく
手をあわせ 願いを投じました

Y軍曹いわく 今日この地に私達が来たことは 何か意味のある
今後必要な事 だそうです(^^)
ありがとう Yちゃん(^^)

続きを読む
2014年2月撮影 南城市佐敷(航空自衛隊知念分屯基地内)
もともとは佐敷城の崖下にあったが災害で倒壊した為
1700年代に現在の位置に建設したそうです。
「シックスセンス友人Yちゃん」に案内され行って来ました
基地の中にあるなんて思いもしない
話によると以前 友人Yちゃんは 読谷伊良嶺にある 尚巴志の墓から
尚巴志王をおんぶして この地に降ろしたそうです。
なんか お告げがあったぽいです。不思議です ・・・
・・・
基地内ですが 「拝みに来ました。」と入り口で手続きすれば
誰でも入れて貰えると思います(警備の人もついて来ますが )
)

続きを読む
もともとは佐敷城の崖下にあったが災害で倒壊した為
1700年代に現在の位置に建設したそうです。
「シックスセンス友人Yちゃん」に案内され行って来ました
基地の中にあるなんて思いもしない

話によると以前 友人Yちゃんは 読谷伊良嶺にある 尚巴志の墓から
尚巴志王をおんぶして この地に降ろしたそうです。

なんか お告げがあったぽいです。不思議です
 ・・・
・・・基地内ですが 「拝みに来ました。」と入り口で手続きすれば
誰でも入れて貰えると思います(警備の人もついて来ますが
 )
)
続きを読む
自前の125ccのスクーターでプチツーリングしたんですが
軽量級は風圧きついですえ〜
風の強い海岸線は最悪です 飛ばされてしまいそう
やっぱり中量級以上じゃないと風に負けてしまうんだよねえ〜
ピロッとHP開いたら CTX700が目に止まった
いいんじゃない?中重量級 それに洗礼された操作性のホンダ(^^)
270°クランク2気筒エンジン(^^)じゃが?
国産だけに鼓動感の味付けは疑問ですが?
何処か試乗車試しにいこうかなああ〜(^^)
ホンダHP抜粋
PGM-FI採用669cm3水冷直列2気筒。低回転域から豊かでフラットなトルクを発揮するとともに、270°位相クランクの採用により、味わいある心地良い鼓動感〜

軽量級は風圧きついですえ〜
風の強い海岸線は最悪です 飛ばされてしまいそう

やっぱり中量級以上じゃないと風に負けてしまうんだよねえ〜
ピロッとHP開いたら CTX700が目に止まった

いいんじゃない?中重量級 それに洗礼された操作性のホンダ(^^)
270°クランク2気筒エンジン(^^)じゃが?
国産だけに鼓動感の味付けは疑問ですが?
何処か試乗車試しにいこうかなああ〜(^^)
ホンダHP抜粋
PGM-FI採用669cm3水冷直列2気筒。低回転域から豊かでフラットなトルクを発揮するとともに、270°位相クランクの採用により、味わいある心地良い鼓動感〜

1416年 最後の山北王 攀安知(はんあんち)は 中山軍の思紹、
尚巴志との戦いに敗れ 自害の際 代々相伝の宝刀 千代金丸を
志慶真川に捨てたがその後発見され尚王家に渡ったそうです。
現在は那覇市歴史博物館にあるそうだが、即見学だと思いきや
博物館が展示期間があるらしく、残念な事に期間を逃してしまった
山北王統 代々相伝の宝刀となると600〜700年の骨董品(^^)
次の機会は逃さない


Wikipedia抜粋
千代金丸(ちよがねまる)の指定名称は、「金装宝剣拵 刀身無銘(号 千代金丸)」。
刃長71.3センチ。刀身は平造りで庵棟、やや細身で先反り強くつく。地金は板目肌流れる。刃文は広直刃調、小互の目交じり、足葉入る。帽子は直ぐに先尖りごころに反り、長く焼き上げる。彫物は表裏に五本の細樋。無銘であるが、16世紀の作かという推定もある。
拵えの全長は92.1センチ。古代の頭椎太刀のような形の金製兜金が付いた柄で、「大世」[1]の銘が刻まれている。鍔は赤銅地で木瓜型の板鍔、四方に四花型と猪の目形の透かしを入れ、鍍金毛彫り菊文を散らす。鞘は黄金色に輝く華麗なものである。柄は片手用で、琉球独自の拵えである。
伝来は「千代金丸宝刀ノ由来」によれば、尚巴志により攻め滅ぼされた北山王攀安知[2]の所持した宝刀で、城を守りきれなかったことに怒って、守護の霊石を切りつけ、更にこの刀で自害しようとしたが、主の命を守る霊力が込められた刀であり、死にきれず、重間(志慶間)川に投げ捨ててから命を絶った。これを伊平屋の住人が拾い上げて中山王に献上したという。
尚巴志との戦いに敗れ 自害の際 代々相伝の宝刀 千代金丸を
志慶真川に捨てたがその後発見され尚王家に渡ったそうです。
現在は那覇市歴史博物館にあるそうだが、即見学だと思いきや
博物館が展示期間があるらしく、残念な事に期間を逃してしまった

山北王統 代々相伝の宝刀となると600〜700年の骨董品(^^)
次の機会は逃さない



Wikipedia抜粋
千代金丸(ちよがねまる)の指定名称は、「金装宝剣拵 刀身無銘(号 千代金丸)」。
刃長71.3センチ。刀身は平造りで庵棟、やや細身で先反り強くつく。地金は板目肌流れる。刃文は広直刃調、小互の目交じり、足葉入る。帽子は直ぐに先尖りごころに反り、長く焼き上げる。彫物は表裏に五本の細樋。無銘であるが、16世紀の作かという推定もある。
拵えの全長は92.1センチ。古代の頭椎太刀のような形の金製兜金が付いた柄で、「大世」[1]の銘が刻まれている。鍔は赤銅地で木瓜型の板鍔、四方に四花型と猪の目形の透かしを入れ、鍍金毛彫り菊文を散らす。鞘は黄金色に輝く華麗なものである。柄は片手用で、琉球独自の拵えである。
伝来は「千代金丸宝刀ノ由来」によれば、尚巴志により攻め滅ぼされた北山王攀安知[2]の所持した宝刀で、城を守りきれなかったことに怒って、守護の霊石を切りつけ、更にこの刀で自害しようとしたが、主の命を守る霊力が込められた刀であり、死にきれず、重間(志慶間)川に投げ捨ててから命を絶った。これを伊平屋の住人が拾い上げて中山王に献上したという。